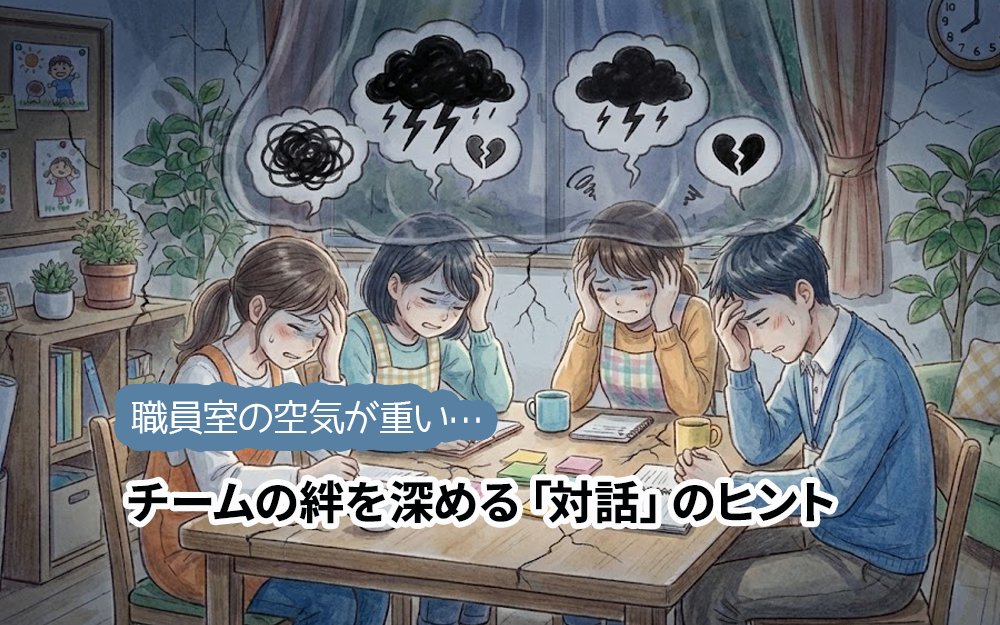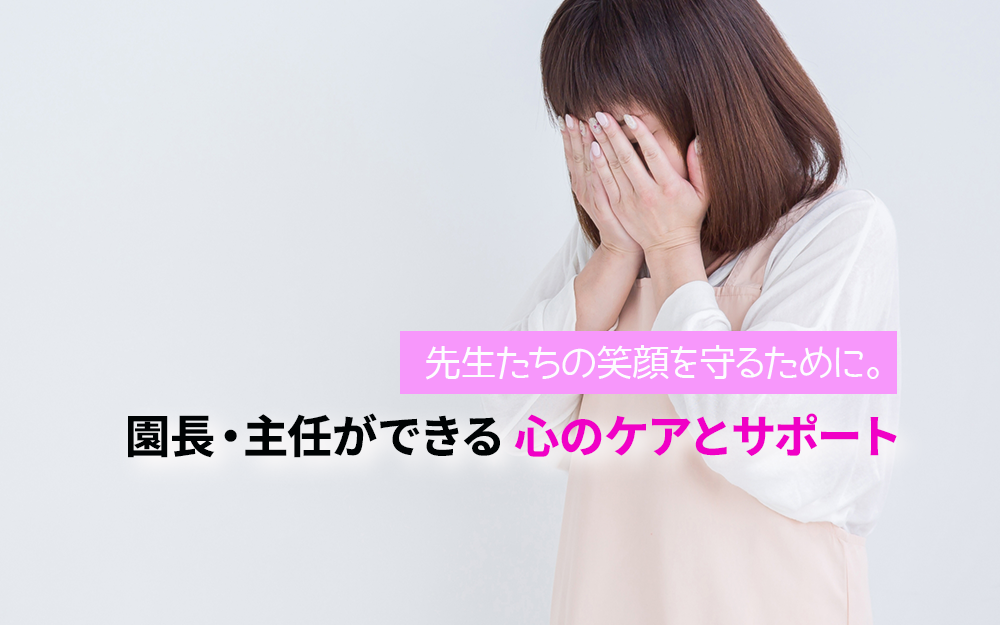「保育の質には自信があるのに、なぜか魅力が伝わりきっていない気がする…」
「SNSを頑張ってはいるけれど、なかなか入園の問い合わせにはつながらなくて…」
もし、そんな風に感じているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。
高額な広告費をかける必要はありません。大切なのは、園が持つ素敵な「らしさ」を、一貫した言葉と想いで、地域の方々へ丁寧に届けていくこと。このページでは、園長先生や主任の先生、そして現場の保育士たちが「これなら明日からできそう!」と思える具体的なステップに分けて、その方法をご紹介します。
この記事のもくじ
【準備編】
うちの園「らしさ」と「届けたい想い」は?
「情報発信を始めよう!」と思っても、いきなりSNSを開く前に、少しだけ立ち止まってみませんか? この章では、すべての土台となる「うちの園のらしさ」をみんなで見つけるヒントをご紹介します。自分たちの想いを言葉にし、届けたい相手の気持ちに寄り添う。ここから、心に響く情報発信が始まります。
まずは「うちの園らしさ」を言葉にしてみませんか?
「ブランディング」と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、要は 「私たちは、どんな保育を大切にしている園なんだろう?」を、みんなで言葉にしてみる 作業です。ロゴやテーマカラーを決めることだけが、ブランド作りではありません。
一度、保育士たちと90分ほどの時間をとって、こんなおしゃべりをしてみませんか?
例えば、「私たちの使命はなんだろう? なぜこの園はここにあるんだろう?」と考えてみたり、「どんな子どもたちを育てたいか、その未来の姿」を想像してみたり。日々の保育でみんなが「大切にしたい3つのこと」や、園をひと言で表す「キャッチコピー」を出し合うのも楽しい時間です。
さらに、「手作りの給食が自慢!」「木のぬくもりが感じられる園舎が好き」といった、保育士一人ひとりが感じる“ここが自慢!”なポイントを集めてみるのもいいですね。
ここで生まれた言葉たちが、これからの情報発信の「ブレない軸」になります。ホームページ、SNS、園だより、見学にいらした方への説明まで、 繰り返し同じ言葉で 伝えていくこと。それが「伝わる」ための、シンプルですが一番大切な一歩です。
保護者の方は、どうやって園を探すんだろう?
地域にお住まいの保護者の方が、入園を決めるまでの道のりを、少し想像してみましょう。
まず、保護者の方は「うちの近所で、評判のいい園はどこかな?」とマップ検索や口コミで園の存在を 知る ことから始めます。
次に、SNSの日常的な投稿を見て「園の雰囲気や保育士さんの人柄はどうかな?」と 信頼 できるかどうかを確かめます。
そして、いくつかの園のホームページを見ながら「給食は? 延長保育は?」と具体的な情報を 比べ 、最終的に「一度、見学に行ってみたい!」と園庭開放への参加や見学を申し込むという 行動 に移るのです。
それぞれの段階で、保護者の方が知りたい情報は少しずつ違います。だからこそ、ホームページやSNSの役割分担を決めておくことが、とても効果的なんです。
文章のトーンを揃えて、“園らしい声”を届けよう
まるで“園だより”を書くときのような、温かい言葉選びを心がけてみませんか?
「〇〇をさせました」と書く代わりに、「〇〇ちゃんが“もう一回!”と、何度も挑戦していましたよ」と子どもの姿を描写する。
活動のねらいや、「お家でも試してみてくださいね」というご家庭への橋渡しの一言を添える。
こうした小さな工夫が、園の“声”となり、ファンを増やしていきます。
【実践編】
ホームページ・SNS・地域交流で魅力を伝える
届けたい想いが固まったら、いよいよ実践です。この章では、園の魅力を伝えるための3つの舞台、①信頼の“顔”となる『ホームページ』、②日々の“体温”を伝える『SNS』、③温かい“輪”を広げる『地域とのつながり』について、具体的なアイデアをたっぷりご紹介します。明日からすぐに試せるヒントを見つけてください。
ホームページは“園の顔”。安心して訪れてもらうための整え方
SNSが新しい出会いの場だとしたら、 ホームページは「この園に決めた!」と思っていただくための、一番大切な場所 です。訪問してくれた方が、安心して園のことを知れるように、いくつかのポイントを整えておきましょう。
まず、訪問者が最初に目にする トップページ では、園のキャッチコピーと大切にしている想いを、温かい写真と共に伝えましょう。
次に、 園の特色 ページでは、自慢の食育や遊びへの考え方を、専門用語を避けて分かりやすく紹介します。
保護者の方が特に知りたい 一日の流れや年間行事 は、園での暮らしが目に浮かぶように具体的に書くのがポイントです。
もちろん、 料金やアクセス といった実用的な情報も、問い合わせの前に不安を解消できるよう、丁寧に記載しておくと親切ですね。
そして、見学のご案内や採用情報も、それぞれのページでしっかりと想いを伝えていきましょう。
また、Googleマップなどで「〇〇市 保育園」と探した時に、自分たちの園をしっかり見つけてもらうための工夫も大切です。園の名前と地域名の書き方をサイト全体で統一したり、Googleに登録する情報とホームページの表記を一致させたり、といった地道な作業が効果を発揮します。
SNSは“保育の日常”を届ける舞台
SNSの主役は、なんといっても現場の先生方です。それぞれのSNSの得意なことを活かして、園の日常を伝えてみましょう。
例えば、写真がメインの Instagram は、園の温かい雰囲気を伝える“アルバム”のように使えます。日々の活動写真に、保育のねらいや家庭でできる遊びのヒントを一行添えるだけで、ぐっと深みが出ますよ。
子どもたちの元気な声や夢中で遊ぶ姿を伝えるなら、 YouTube のショート動画がぴったりです。何気ない日常が、保護者にとっては貴重な情報になります。
そして、園庭開放のお知らせなど確実に届けたい情報は LINE公式アカウント で。予約フォームへのリンクを送れば、行動をそっと後押しできます。
X(旧Twitter)やFacebook は、地域のイベント情報を紹介するなど、地域とのつながりを作るのに向いていますね。
大切なのはフォロワー数よりも、投稿への「いいね!」や「保存」、そして「見学してみたいです」という実際の反応です。
インターネットを飛び出して、地域とつながる
情報発信は、ネットの中だけで終わりません。地域でのリアルなつながりを作り、そこからホームページやSNSへ誘導する流れをイメージしてみましょう。
「毎月第2・第4水曜日は、〇〇保育園の園庭開放の日!」のように、地域の親子が気軽に立ち寄れるイベントを定例化するのはいかがでしょうか。また、地域の商店街や図書館、子育てひろばにお願いしてポスターやチラシを置かせてもらったり、一緒にイベントを企画したりするのも素敵なつながりを生みます。まだ園に通っていない親子向けの公開保育や食育体験を開き、その場で園見学の予約へつなげるのも良い方法です。
連携先に、イベントの写真やレポートをお礼として提供すると、相手のSNSでも紹介してもらえ、つながりがさらに広がっていきますよ。
【継続編】
無理なく続ける「チームの仕組み」「安心のルール」
「大事なのは分かるけど、続けるのが一番大変…」それが現場の本音かもしれません。この章では、そんな保育士たちが無理なく、そして何より安心して情報発信を続けるためのヒントをお伝えします。一人で頑張らないためのチームの仕組みづくりと、子どもたちを守るための大切な約束ごと。継続のための“お守り”になるはずです。
何より大切にしたい、“安心”への配慮
情報発信をする上で、子どもたちのプライバシーと安全への配慮は、何よりも優先したいこと。
入園時に写真などの広報利用について書面で丁寧に確認することはもちろん、名札などが写り込まないようにする一手間が大切です。
また、遊具で遊ぶ写真などに「保育士が見守る中、安全に配慮して行っています」といった一言を添えるだけで、保護者の安心感は大きく変わります。
もしもの時のために、削除要請があった場合の対応手順などをあらかじめ園で決めておくと、いざという時に慌てずに済みます。
無理なく続けるための“チーム体制”のヒント
「大事なのは分かるけど、日々の保育で手一杯…」それが現場の本音だと思います。
だからこそ、一人で抱え込まず、チームで楽しく続ける仕組みを作りましょう。
例えば、 企画 は園長先生や主任の先生が週に1回10分でテーマを決め、 写真撮影 は各クラスの保育士が「1日3枚まで」のようにルールを決めて無理なく行います。そして、 投稿作業 は広報担当の保育士が時間を決めて担当し、最後に副園長先生が 最終チェック をする、といった形です。
使うツールも、みんなが使える簡単なもので十分。月ごとの投稿カレンダーを作っておけば、ネタ切れの心配もありません。
万が一のときこそ、園の誠実さが伝わるチャンス
どんなに気をつけていても、トラブルが起きる可能性はゼロではありません。大切なのは、そんな時に慌てず、隠さず、真摯に向き合う姿勢です。
迅速に事実を確認し、園長先生の名前で責任をもって報告・対応する。その誠実な姿が、かえって地域からの信頼を深めることにもつながります。
【発展編】
見学・入園につなげる「最後のひと押し」「90日計画」
せっかく発信するなら、素敵な出会いにつなげたいですよね。この章では、積み重ねてきた発信を、実際の「見学」や「入園」という成果に結びつけるための具体的な方法をご紹介します。興味を持ってくれた保護者の方をスムーズにご案内する“丁寧な道しるべ”の作り方と、最初の90日間で成果を出すための行動計画。ゴールまでの道のりを一緒に見ていきましょう。
“最後のひと押し”で、見学・入園へつなげる
興味を持ってくれた方を、迷わせずに入園までご案内する“丁寧な道しるべ”も大切です。
見学の予約フォームは入力項目をできるだけ少なくし、予約完了メールには当日の持ち物や地図を添えておく。
見学後には感謝のメールを送って不安な点がないかフォローする。
この“最後のひと押し”が、保護者の方の決断を、温かくサポートします。
まずは90日間!小さな成功体験を積み重ねるロードマップ
いきなり全部やろうとせず、まずは3ヶ月の計画で、できることから始めてみませんか?
最初の1週間 は、まず土台づくりから。園の「らしさ」を言葉にする会議を開き、ホームページの案内ページを整えましょう。そこから 1ヶ月目 には、いよいよSNSの週3回投稿をスタート。園庭開放の年間スケジュールも公開できるといいですね。
続く 2ヶ月目 は、少し外に目を向けて、地域の商店街や図書館にチラシを置いてもらえないかお願いに回るなど、地域連携を始めます。
そして 3ヶ月目 になったら、一度立ち止まって振り返りを。どんな投稿の反応が良かったかをみんなで話し合ったり、保護者の方に簡単なアンケートをお願いしたりして、改善のヒントを見つけていきましょう。
日々の保育こそ、最高の“らしさ”
“いい園なのに、魅力が伝わらない”——その差は、特別なセンスがあるかどうかではありません。
園が大切にしている想いを、同じ言葉で、同じ熱量で、コツコツと発信し続けること。その**一貫性**こそが、園の「らしさ」を地域に届け、信頼を育んでいきます。
難しく考えすぎなくても大丈夫です。まずは、園のキャッチコピーをみんなで考え、ホームページの案内を分かりやすくし、週3回のSNS投稿を始めてみませんか? 90日後には、きっと見学の問い合わせや、地域からの温かい眼差しに、目に見える変化が生まれているはずです。
広報は、特別な誰かがやる難しい仕事ではありません。保育士たちが日々、子どもたち一人ひとりと真剣に向き合っている、その温かい眼差しこそが、最強のブランディングなのですから。
【巻末付録】
すぐに使える!投稿見出し&フレーズ集
困ったときのために、いくつかフレーズの例を置いておきますね。
- 「雨の日の“音さがし”|3歳児クラスの発見」
- 「小麦粉ねんどで“形の会話”|5歳児クラスの創造力」
- 「園庭開放のお知らせ|親子で一緒に泥んこ遊びしませんか?」
職員室の空気が重い…チームの絆を深める「対話」のヒント
「なんとなく職員室の空気が重い」「情報の伝達ミスが続いている」「特定の職員同士がギクシャクしている…」 子どもたちの笑顔を守る保育の現場で働く「大人たち」の人間関係に悩まれる経営者や園長先生も多いよう…
先生たちの笑顔を守るために。園長・主任ができる心のケアとサポート
大切な仲間である保育士さんたちの「心の健康(メンタルヘルス)」を守るために、管理職に何ができるのか、今日から始められる具体的なアクションを一緒に考えていきましょう。
書類業務が多すぎる!業務効率を上げるICT導入のリアル
絡帳の手書き、登降園記録の転記、保育日誌の作成…ICT化の波が広がっています。神奈川県内の具体的な導入事例、導入のメリット・注意点を紹介します。


 ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。
ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。