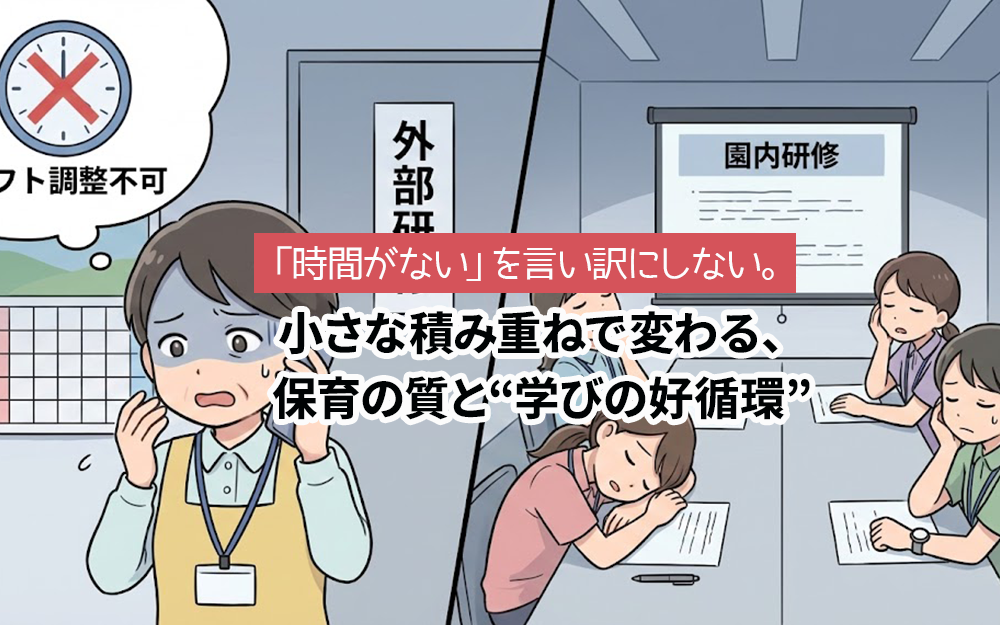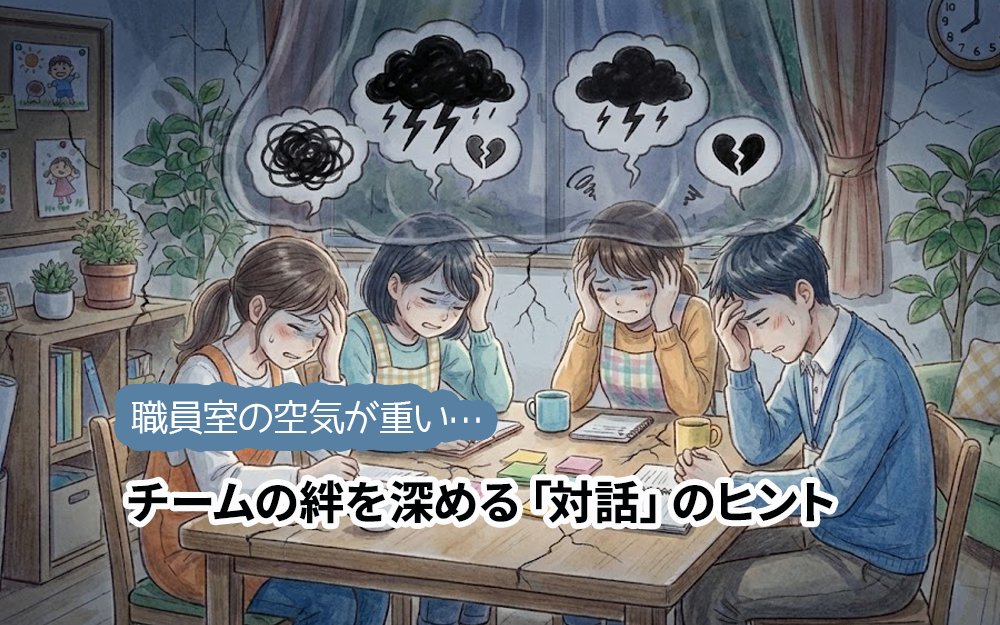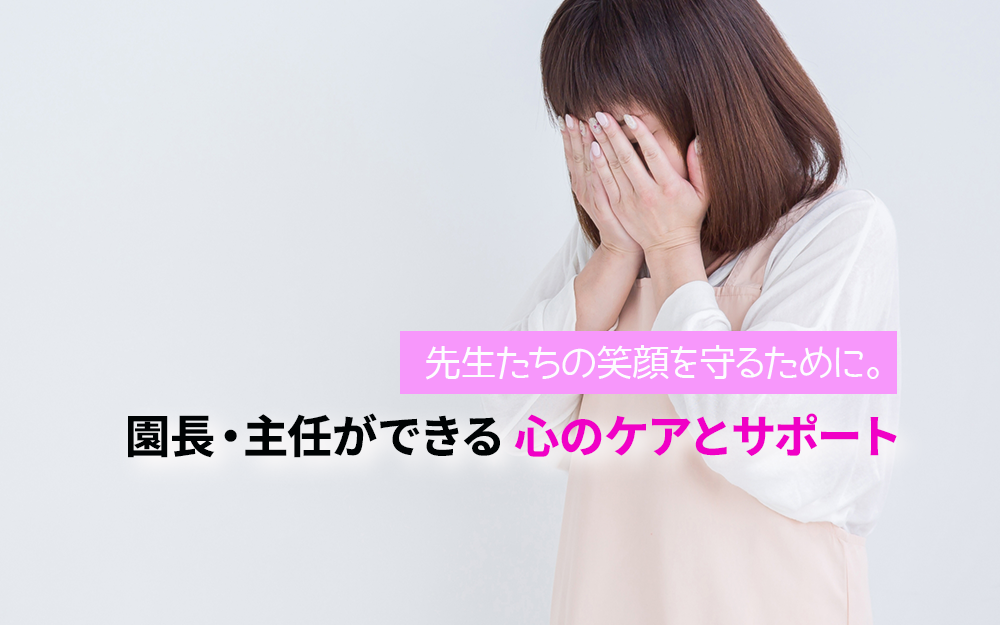「また保護者から呼び出された」「連絡帳の書き方にクレームが来た」「こんな言い方をされて心が折れそう」——保育の仕事って、子どもと向き合うことが中心だと思われがちですが、実際には保護者対応にかかる時間や精神的負担が本当に大きいですよね。
厚生労働省の調査でも、保育士の業務上の悩みとして「保護者対応・苦情対応」を挙げた人が45.1%と、人間関係や多忙感と並んで上位に位置しています。この記事では、保護者対応に疲れない園づくりのための具体的な方法をお伝えします。明日からでも実践できる内容ばかりですので、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事のもくじ
保護者対応がストレスになる3つの理由
保護者対応が私たちの負担になってしまうのには、実はよくあるパターンがあります。
一人で抱え込んでしまう
例えば、ある先生のクラスで「うちの子だけお迎えの時に泣いている。先生の対応が悪いのでは?」というクレームがあったとします。
こんなとき、先生は「自分のクラスだから」と一人で解決しようとしてしまいがちです。
でも実は、お迎え時に泣く子への対応って、園全体で統一した方法があった方が良いケースがほとんどなのではないでしょうか。一人で悩んでいると感情的になりやすくなったり、「私のせいかも」と必要以上に落ち込んでしまうことも多いですよね。
また、先生が一人で対応した内容を他の先生が知らないと、後で別の先生が同じ保護者と話をした時に「前に聞いた話と違う」なんてことになって、さらに混乱してしまいます。
どう対応すれば良いか分からない
「こういう時はどうすればいいの?」という疑問、ありませんか?
例えば、保護者から「他の子に噛まれた。相手の子の名前を教えて」と言われた時、新人の先生は「個人情報だから言えません」と答えていいのか、「主任に確認します」と言うべきなのか迷ってしまいます。
園によって対応がバラバラだと、先生によって言うことが違って保護者を混乱させてしまうこともあります。特に新人の先生は「どこまで自分で判断していいの?」「いつ上司に相談すべき?」が分からなくて、不安を抱えたまま対応することになりがちです。
問題が起きてから慌てて対応している
保護者から「実は前から気になっていたのですが…」と大きなクレームを言われてから「えっ、そんなことを思っていたの?」と慌てて対応を始めたことはありませんか?
でも、問題が大きくなってからでは、保護者の不満もかなり溜まってしまっていて、解決するのにとても時間がかかってしまいます。普段から「何か気になることはありませんか?」と聞く機会があれば、小さなうちに解決できるはずです。
みんなで支え合う体制づくり
個人の頑張りに頼るのではなく、園全体でみんなをサポートする体制があれば、負担はぐっと軽くなります。
誰が対応するかをあらかじめ決めておく
横浜市の「教育・保育施設等における苦情対応ガイドライン」では、こんな風に役割分担することが勧められています。
例えば「連絡帳の件で質問があります」程度なら担任が対応、「先生の対応について納得できません」という苦情なら主任が入る、「園の方針を変えてほしい」という大きな要望なら園長が責任者として対処する、という感じです。
こうしておくと、担任の先生が「私一人で何とかしなきゃ」と重い責任を背負うことがなくなります。保護者にとっても「きちんとした体制で対応してくれるんだな」という安心感につながりますよね。
「これはちょっと一人では難しそう」と感じたら、迷わず「主任に相談してみますね」と言えるような雰囲気を作ることが大切です。
やり取りをメモに残して共有する
札幌市の「保育所における苦情対応マニュアル」では、「誰が・いつ・何を言われたか・どう答えたか」を必ずメモに残して、職員間で共有することを勧めています。
例えば「○月○日、佐藤さんから『お迎えが遅くなった時の連絡方法について質問あり』→『15分以上遅れる場合は必ず電話をお願いしますとお答えした』」といった感じで、簡単でも記録を残しておきます。
こうしておくと、同じようなことを他の保護者に聞かれた時も一貫した対応ができますし、担任が変わる時の引き継ぎもスムーズになります。毎月の職員会議で「最近こんなことがありました」と共有すれば、みんなで対応のコツを学び合うこともできますね。
最終的に誰が決めるかをはっきりさせる
「結局、誰が最終的に判断するの?」をはっきりさせておくことって、とても大切です。
例えば、保護者から「運動会の日程を変更してほしい」という要望があった時、担任の先生が「私では決められません」と言い続けていると、保護者もイライラしてしまいます。
多くの自治体では、大きな問題については園長または主任が「苦情対応の責任者」として対応することが勧められています。責任者がはっきりしていると、保護者も「困った時は園長先生に相談しよう」と分かりやすくなりますし、私たち職員も安心して「園長に確認してお答えします」と言えるようになります。
小さな不満のうちに気づく工夫
大きなクレームになる前に、「ちょっと気になる」程度のうちに気づいて対処できれば、みんなが楽になります。
気軽に意見を言ってもらう仕組みを作る
守口市の「保育施設運営ガイドライン」では、年1回のアンケートだけじゃなくて、いつでも気軽に意見を言ってもらえるような工夫をすることが勧められています。
例えば、園だよりにQRコードをつけて「何かお気づきの点があれば、こちらからお気軽にどうぞ」とスマホで簡単に意見を送れるようにしたり、玄関に意見BOXを置いて「ちょっとしたことでも教えてください」と書いておいたりします。
保護者の方も「先生、お忙しそうだし、こんな小さなことで声をかけるのも…」と遠慮していることって結構あるのです。気軽に伝えられる方法があれば、大きな問題になる前に「実は気になっていることがあって…」と教えてもらえるようになります。
普段の会話で変化に気づく
送迎時の「おはようございます」「お疲れさまでした」といった挨拶や、連絡帳でのやり取りの中で、保護者の表情や言葉の雰囲気が「いつもと違うかな?」と感じることってありませんか?
例えば、いつもニコニコ挨拶してくれるレナちゃんのお母さんんが、最近何となく表情が硬いような気がする…そんな時は「お疲れのようですが、何かお困りのことはありませんか?」と優しく声をかけてみましょう。
「実は最近、家で園の話をしたがらなくて心配で…」なんて小さな心配事を話してもらえるかもしれません。こうした段階で相談してもらえれば、「一緒に様子を見てみましょうね」と穏やかに対応できます。
「何となく様子が違う」サインを見逃さない
保護者の不満が溜まっている時って、実は小さなサインが出ていることが多いのです。
例えば、いつも元気よく「おはようございます!」と言ってくれていたケンタ君のお母さんが、最近は軽く会釈だけになった。連絡帳にいつも「今日もありがとうございました」と書いてくれていたるりちゃんのお母さんが、最近は必要最小限のことしか書かなくなった。運動会の準備を積極的に手伝ってくれていたマリちゃんのお父さんが、最近は「忙しくて」と参加を避けるようになった。
こうした変化を複数の職員が「あれ?」と感じた場合は、職員間で情報を共有して、適切なタイミングで「何かお困りのことはありませんか?」と声をかけてみることが大切です。
クレームを受けた時の上手な対応方法
どんなに気をつけていても避けられないクレームもあります。でも、上手な対応方法を知っていれば、ストレスも軽くなります。
まずは気持ちを受け止める
例えば「うちの子が他の子に叩かれたのに、先生は見ていなかった。どういうことですか?」と怒った保護者がいたとします。
そんな時、つい「でも、私たちも一生懸命見ているんです」と言い訳したくなりますが、まずは保護者の気持ちを受け止めることから始めましょう。
「お子さんが嫌な思いをされて、本当に申し訳ありませんでした。お母さんもご心配だったと思います」
と、まずは保護者の気持ちに寄り添います。
保護者が感情的になっている時は、「お子さんのことを大切に思ってくださっているお気持ち、よく分かります」「ご心配をおかけして申し訳ありません」といった言葉で、まずは気持ちを落ち着かせることを最優先にしましょう。
何が起こったかを整理する
保護者の話を聞いた後は、「いつ・どこで・何が起こったか」を整理します。例えば「昨日の午後、園庭での自由遊び中に、滑り台の近くで○○ちゃんが△△くんに叩かれた」という具体的な状況を確認します。
その場にいた職員からも「その時の状況はどうでしたか?」と聞いて、いろいろな角度から何が起こったかを把握します。この時、職員を責めるのではなく、「より良い対応を見つけるために教えてね」というスタンスで聞くことが大切です。
保護者の「うちの子だけがいつも叩かれている」という感情と、実際に起こった「昨日1回、他の子とトラブルがあった」という事実を分けて考えることで、適切な対応策が見えてきます。
一緒に解決策を考える
事実がはっきりしたら、「どうしたら同じことが起こらないようにできるか」を保護者と一緒に考えましょう。
例えば「滑り台の周りでトラブルが起きやすいので、職員の見守り位置を工夫します」「お子さんが困った時に職員に伝えやすいよう、合言葉を決めましょう」といった具体的な改善策を提案します。
「こうしますね」と一方的に決めるのではなく、「このような対策を考えているのですが、他にもご希望があれば教えてください」と相談する形にすると、保護者も納得しやすくなります。
決まった改善策については、「来週から実行して、1週間後にまた様子をお聞かせください」というように、いつまでにどのように実行するかを具体的に約束しましょう。
職員のストレスを軽くするサポート
保護者対応でのストレスを軽くするには、技術的な対応方法だけじゃなくて、心のサポートも大切です。
みんなでフォローし合う
大変な保護者対応をした職員を一人ぼっちにしないよう、チーム全体でサポートする雰囲気を作りましょう。
例えば、難しいクレーム対応をした田中先生に「本当にお疲れさまでした」「大変でしたね」と声をかけることから始めます。
対応が終わった後は、「今回の対応で良かった点はどこだと思う?」「次はどうしたらもっと良くなるかな?」とみんなで振り返る時間を作ります。「ダメ出し」ではなくて、「一緒に学ぼう」という気持ちで話し合うことが大切です。
新人の先生には、ベテランの先生が一緒について「こういう時はこう対応するといいよ」とアドバイスできる体制があると安心ですね。
練習や勉強でスキルアップ
保護者対応って、経験だけじゃなくて、練習や勉強でスキルアップできるものです。
例えば、外部の専門家を招いて「保護者対応の基本」を学ぶ研修を受けたり、他の園での成功事例を教えてもらったりしましょう。
園内でも「もしこんなクレームがあったら、どう対応する?」とみんなで考える時間を作ると効果的です。実際にロールプレイングで「保護者役」と「職員役」に分かれて練習しておくと、本番でも「あ、これ練習したやつだ」と思えて、緊張が和らぎます。
一人で抱え込まないための工夫
保護者対応でのストレスって、一人で我慢していると、どんどん辛くなってしまいます。定期的に「最近どう?困ったことない?」と気軽に相談できる機会を作りましょう。
職員同士でも「実はこんなことがあって…」と相談し合える雰囲気作りが大切です。「辛い時は一人で我慢しないで、みんなに話してね」という文化を作ることで、深刻になる前に対処できます。
必要に応じて、外部のカウンセリングサービスの利用も検討してください。私たちの心の健康を守ることは、結果的に子どもたちへの保育の質を向上させることにもつながります。
園全体で支え合う気持ちを共有しよう
保護者対応のストレスを減らすには、一人だけが頑張るのではなく、園全体で「みんなで支え合おう」という気持ちを共有することが何より大切です。
厚生労働省や各自治体が出しているガイドラインには、実際の現場で「これは効果があった!」という工夫がたくさん詰まっています。こうした実例を参考にしながら、自分たちの園に合った形にアレンジしていけば、「クレームが怖くない園」「保育士が安心して働ける園」を作ることができます。
保護者対応は確かに大変ですが、適切な方法を知っていれば、保護者との信頼関係を深めるチャンスにもなります。一人で抱え込まずに、みんなで支え合いながら、子どもたちにとっても保護者にとっても、そして私たち職員にとっても居心地の良い園を作っていきましょう。

「時間がない」を言い訳にしない。小さな積み重ねで変わる、保育の質と“学びの好循環”
質の高い保育をしている園は、日常の業務の中に「学び」を自然に溶け込ませています。時間や予算をかけなくてもできる、明日からの「職員研修」と「園内での学び合い」のヒントを紹介します。
職員室の空気が重い…チームの絆を深める「対話」のヒント
「なんとなく職員室の空気が重い」「情報の伝達ミスが続いている」「特定の職員同士がギクシャクしている…」 子どもたちの笑顔を守る保育の現場で働く「大人たち」の人間関係に悩まれる経営者や園長先生も多いよう…
先生たちの笑顔を守るために。園長・主任ができる心のケアとサポート
大切な仲間である保育士さんたちの「心の健康(メンタルヘルス)」を守るために、管理職に何ができるのか、今日から始められる具体的なアクションを一緒に考えていきましょう。

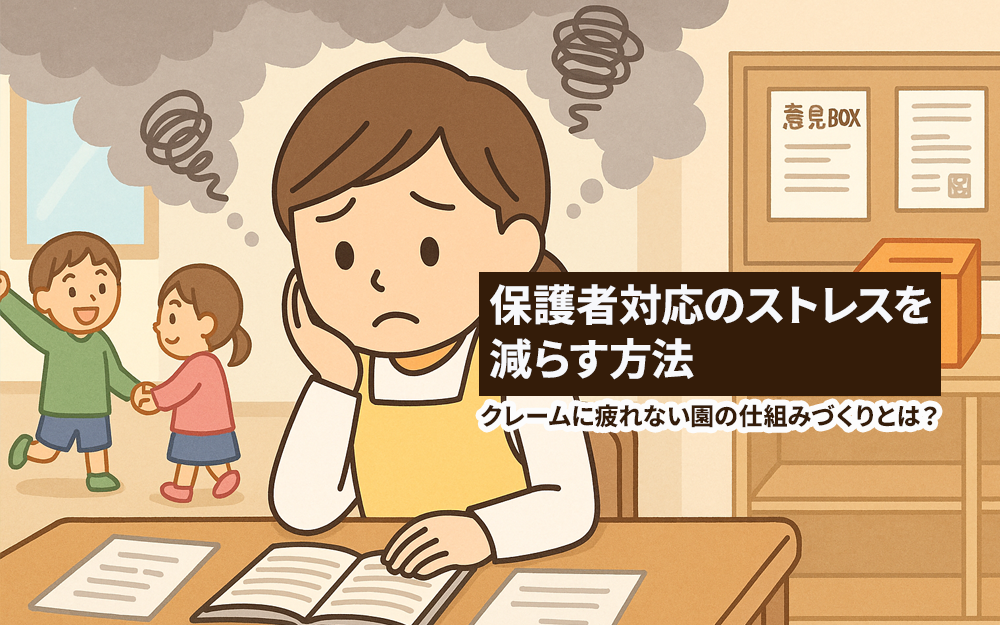
 ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。
ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。