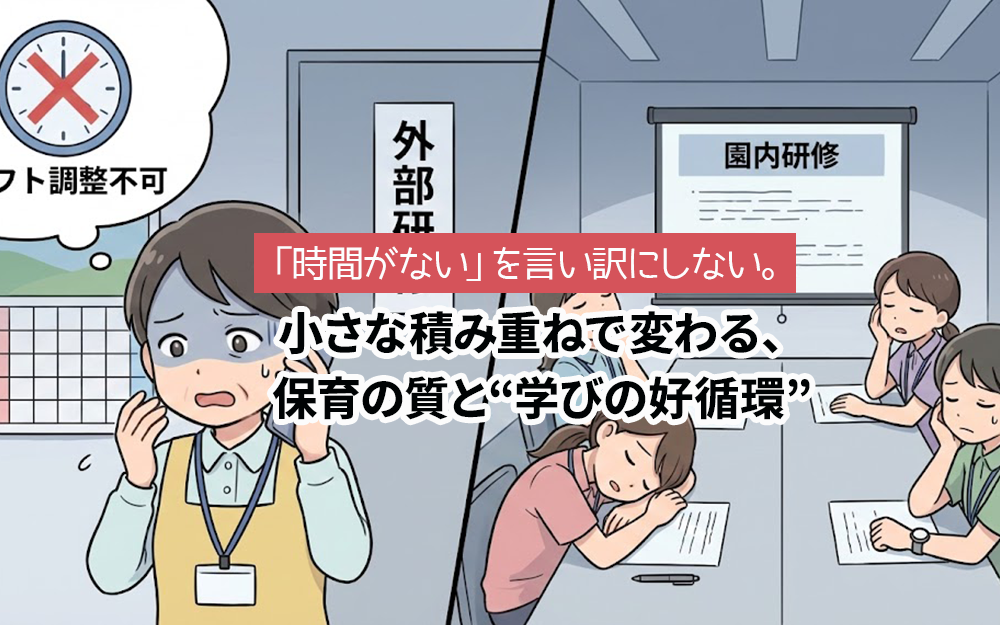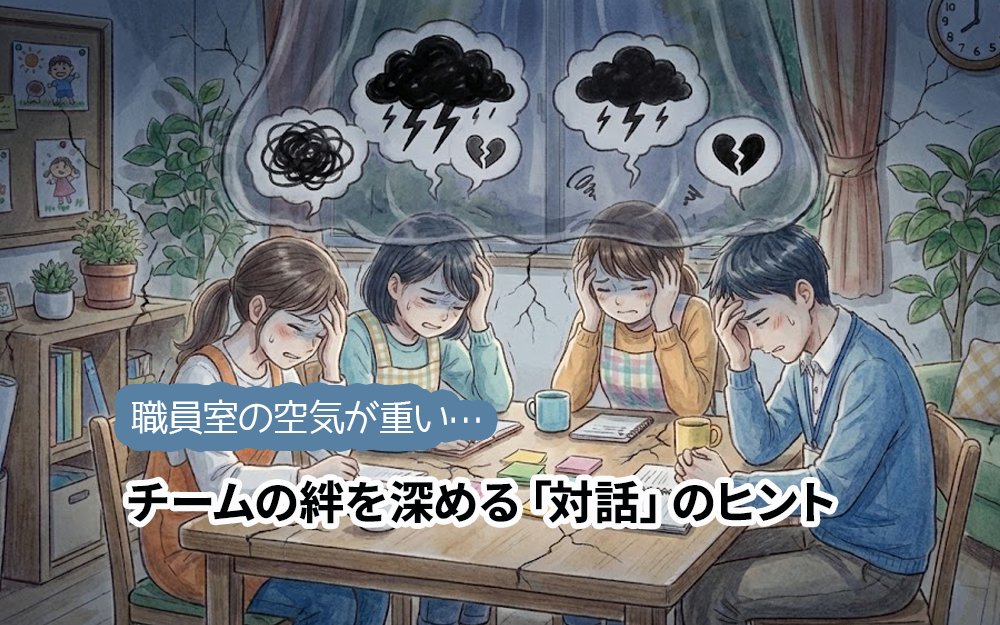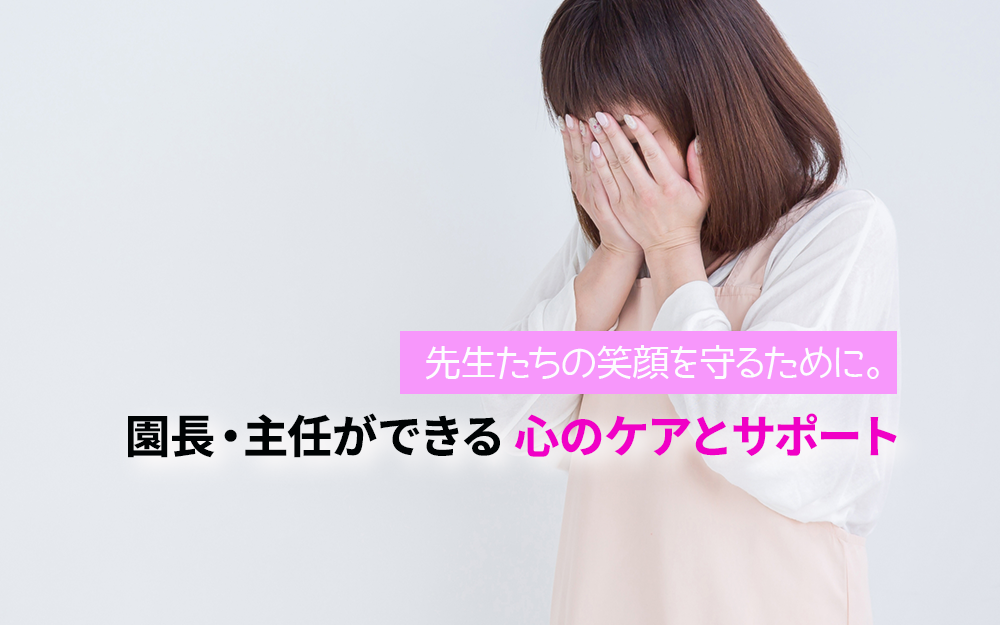保育士の仕事は書類作業が多いですよね。連絡帳の手書き、登降園記録の転記、保育日誌の作成…気がつけば子どもたちと向き合う時間より、書類に向かう時間の方が長くなっていませんか? 全国の保育現場で進むICT化の波は、神奈川県内でも確実に広がっています。実際に導入した園では「もう手書きには戻れない」という声が続々。今回は、神奈川県内の具体的な導入事例とともに、ICT導入の現実的なメリットと注意点をご紹介します。保育の質を高めながら働きやすい環境を作るヒントが見つかるはずです。
この記事のもくじ
毎日の書類地獄から抜け出そう!なぜ今ICTなのか
連絡帳、保育日誌、指導案、要録…終わりのない書類作業に追われる毎日。「また同じことを別の紙に書くの?」という経験、ありませんか。ICT導入は単なる流行ではなく、保育士が本来の仕事に集中するための現実的な解決策です。
こんなに多い!保育園の書類業務あるある
保育現場を支える皆さんなら、日々の書類業務の多さを身をもって感じているでしょう。朝の登園受け入れから始まって、連絡帳への記入、保育日誌の作成、指導案の立案、児童票の更新、要録の作成、勤怠管理、延長保育料の計算、保護者への一斉連絡…挙げればきりがありません。
何回書けば気が済むの?転記作業の罠
特に大変なのが、同じ情報を何度も違う書類に転記する作業です。例えば、ある子どもの様子を保育日誌に書いたら、連絡帳にも書き、月案にも反映させ、個別記録にも残す。手書きの場合、1つの情報を4回も5回も書くことになります。
しかも、急いで書いた文字が読めなくなったり、転記ミスが起きたりと、手間の割に正確性に不安が残ることも。
さらに、保護者対応の電話が鳴れば作業が中断され、お迎え時間の変更連絡を受けたら手帳にメモして、降園時に担当者に伝達して…こうした細かな情報管理も、実は大きな負担になっています。
厚生労働省の調査でも、保育士の勤務時間のうち約3割が事務作業に費やされているという結果が出ており、これが保育士の負担感や離職につながる一因となっています。
子どもと向き合う時間を取り戻したい!
働き方改革が叫ばれる中、保育現場でも業務効率化は待ったなしの課題。ICT(情報通信技術)の活用は、単に「デジタル化すれば楽になる」という話ではなく、保育士が本来の保育業務に集中できる環境を作るための現実的な解決策として注目されています。
実際に導入した園では、残業時間の削減だけでなく、子どもたちと向き合う時間が増え、保育の質向上にもつながっているという報告が相次いでいます。
神奈川県内のICT導入ツールと具体事例
神奈川県内では、自治体の補助制度も後押しして、様々な保育園でICTツールの導入が進んでいます。ここでは、実際に県内で活用されている代表的なツールと、具体的な導入事例をご紹介します。それぞれの園の生の声を聞くことで、導入後の変化をリアルに感じていただけるでしょう。
CoDMON(コドモン)

CoDMONは、保育業界で最も広く使われているICTツールの一つです。
登降園管理、連絡帳、保育日誌、シフト管理、保護者連絡、請求管理など、保育園で必要な機能をワンストップで提供しています。特徴的なのは、スマートフォンアプリとパソコン版の両方に対応していること。保護者は専用アプリで園との連絡ができ、職員はパソコンでしっかりとした記録作業ができる設計になっています。
操作画面は直感的で分かりやすく、PC操作に慣れていない職員でも比較的スムーズに使い始められます。また、園児情報を一度入力すれば、それが連絡帳、保育日誌、登降園記録などに自動で反映される仕組みになっており、転記作業の大幅な削減が可能です。
セキュリティ面でも、個人情報保護に関する各種認証を取得しており、安心して利用できます。
導入事例
湯河原町の保育所4施設では、2025年2月からCoDMONの本格導入がスタートしました。
これまで電話での遅刻・欠席連絡に追われていた朝の時間が、アプリでの連絡により大幅に効率化。「朝一番の電話対応がなくなって、子どもたちを落ち着いて迎えられるようになった」と職員からは好評です。電子連絡帳の導入により、手書きの連絡帳作成時間も短縮され、その分を保育準備や子どもたちとの関わりに充てられるようになっています。
箱根町の認定こども園3園でも、2024年12月からCoDMONの段階的導入が進んでいます。
特に登降園管理システムの効果は大きく、「誰がいつ来て、いつ帰ったか」の把握が正確になり、延長保育料の計算ミスもなくなったそうです。保護者からも「アプリで園の様子が写真付きで見られるのが嬉しい」という声が寄せられています。
横浜市の横浜南プリスクールでは「CoDMONなしでは業務が回らない」と言われるほど、システムが保育業務に深く根付いています。
登降園記録、勤怠管理、連絡帳がすべてデジタル化されたことで、手書き業務が激減。以前は毎日1時間程度の残業が当たり前でしたが、導入後は定時で帰れる日が格段に増えたといいます。職員からは「子どもと向き合う時間が確実に増えた。これが一番大きな変化」という声が聞かれます。
神奈川県内では、川崎市、横浜市、相模原市、大和市、茅ヶ崎市、鎌倉市など多くの自治体でCoDMONの導入が広がっており、公立・私立を問わず幅広い施設で採用されています。
参考 CoDMON(コドモン)- 保育・教育施設向けICTサービス ICT教育ニュース
Hoic(ホイック)

Hoicは横浜市を拠点とする企業が開発した、保育現場の声を徹底的に反映したICTシステムです。
最大の特徴は「使いやすさ」へのこだわり。多くのICTツールが機能の豊富さを売りにする中、Hoicは「本当に必要な機能を、誰でも簡単に使える形で」というコンセプトで開発されています。画面設計はシンプルで分かりやすく、PC操作が苦手な職員でも抵抗なく使い始められると好評です。
登降園管理では、ICカードやバーコードでの打刻に加え、手動入力も可能で、様々な運用形態に対応。保育日誌機能では、定型文の活用により記録時間を大幅に短縮できます。また、保護者向けアプリでは連絡帳機能に加え、園からのお知らせ配信や写真共有も可能で、保護者満足度の向上にもつながっています。
導入事例
特に小規模保育園での導入実績が豊富で、限られた職員で効率的に業務を回したい園にとって強い味方となっています。
サポート体制も手厚く、導入時の研修から運用開始後のフォローまで、現場に寄り添ったサポートを提供しています。
横浜市内の複数の認可保育園で導入されており、「現場の実情を分かってくれているシステム」として高い評価を得ています。
参考 ホイック
Ni+保育園管理システム

Ni+保育園管理システムは、日興テクノス株式会社が提供する保育園専用の管理システムです。
最大の特徴は、インターネット環境がない場所でも利用できるスタンドアロン機能を備えていること。ネットワーク環境に不安がある園でも安心して導入できます。また、既存の保育システムからのデータ移行サポートも充実しており、「今使っているシステムから乗り換えたい」という園のニーズにも対応しています。
園児管理機能では、個別の成長記録から健康管理まで一元化して管理可能。登降園打刻はICカード、バーコード、手動入力など複数の方法に対応しており、園の運用方針に合わせて選択できます。保育日誌や各種帳票の自動生成機能も充実しており、月末の集計作業が格段に楽になったという声が多く聞かれます。
導入事例
延長保育料の自動計算機能は特に好評で、複雑な料金体系でも正確に計算してくれるため、保護者への請求ミスがなくなったと評価されています。
横浜市、川崎市、藤沢市、海老名市、綾瀬市など神奈川県内の多くの自治体で利用実績があり、公立保育園での導入事例も豊富です。
特に、自治体の規定に合わせたカスタマイズ対応力が評価されており、「うちの園の運用に合わせてくれる」という安心感があります。
参考 日興テクノス株式会社
ICT導入による効率化効果とメリット
実際にICTを導入した園では、どのような変化が起きているのでしょうか。数値として現れる効果はもちろん、職員や保護者の満足度向上など、目に見えない部分での改善も大きいようです。ここでは、具体的な効果とメリットを詳しく見ていきましょう。
転記や紙作業の削減
最も実感しやすいのが、転記作業の大幅な削減です。
CoDMONを例に取ると、園児台帳に登録された基本情報(名前、年齢、アレルギー情報など)が、連絡帳、保育日誌、登降園記録、個別指導計画など、すべての帳票に自動で反映されます。これまで同じ子どもの情報を何度も手書きしていた作業が、一度の入力で完了するのです。
ある園では、月初めの園児名簿作成に3時間かかっていた作業が、システム導入後は15分で完了するようになったそうです。
また、手書きによる転記ミス(名前の漢字間違い、年齢の記載ミスなど)も皆無になり、保護者からのクレームも減ったといいます。
連絡帳機能では、子どもの写真を撮影してその場でコメントを入力すれば、自動で該当する園児の連絡帳に追加されます。
これまでのように「写真を撮って、現像して、台紙に貼って、コメントを手書きして」という一連の作業が、スマートフォン一つで完結。時間短縮効果は絶大です。
職員の業務負担軽減
横浜南プリスクールの事例では、ICT導入前と後で職員の勤務状況に劇的な変化が見られました。
導入前は平均して1日1時間程度の残業が常態化していましたが、導入後は週2〜3回程度に減少。特に月末の集計作業では、これまで丸一日かかっていた延長保育料の計算が、システムの自動計算により30分程度で完了するようになりました。
勤怠管理の効率化も大きなポイントです。紙のタイムカードや出勤簿での管理では、月末の集計作業が大変でしたが、ICカードでの打刻システム導入により、リアルタイムで勤務時間が把握できるようになりました。
有給休暇の残日数管理も自動化され、職員からの問い合わせに即座に答えられるようになったそうです。
また、保護者からの電話連絡(遅刻、欠席、お迎え時間変更など)がアプリでの連絡に変わったことで、朝の忙しい時間帯の電話対応が激減。職員は子どもたちの受け入れに集中できるようになり、「朝の保育の質が確実に向上した」という声が聞かれます。
保護者との情報共有の質向上
ICT導入により、保護者との情報共有の質と量が大幅に向上します。従来の紙の連絡帳では、限られたスペースに必要最小限の情報しか書けませんでしたが、電子連絡帳では写真付きで詳細な様子を伝えることができます。「今日は砂場でこんな遊びをしました」という文章に加えて、実際に遊んでいる写真があることで、保護者の満足度は格段に高まります。
リアルタイムでの情報共有も大きなメリットです。
けがをした際の報告、体調変化の連絡、園での楽しいエピソードなど、タイムリーに情報を共有できることで、保護者の安心感が向上。
「園での様子がよく分かる」「先生方がしっかり見てくれているのが伝わる」という感想が多く寄せられています。
また、園からの一斉連絡機能により、運動会の連絡、感染症の流行情報、台風時の対応など、重要な情報を確実に全保護者に届けることができるようになりました。
従来の紙の配布物では、カバンの奥で忘れ去られることもありましたが、スマートフォンへの通知により、情報の見落としが大幅に減少しています。
セキュリティ・運用サポート
保育園でICTを導入する際に最も心配されるのが、個人情報の取り扱いです。
HoicやCoDMONなどの主要システムは、プライバシーマーク(Pマーク)やISO27001などの認証を取得しており、厳格なセキュリティ基準をクリアしています。データの暗号化、定期的なバックアップ、アクセス権限の管理など、技術的な対策も万全です。
また、運用サポート体制も充実しており、導入時の研修から日常的な問い合わせ対応まで、専門スタッフがサポートしています。
「システムが止まったらどうしよう」という不安に対しても、24時間対応のサポートセンターや代替手段の準備など、現実的な対策が用意されています。
定期的なシステム更新により、法改正への対応や新機能の追加も自動で行われるため、園側で特別な対応をする必要がありません。
これまで手動で行っていた様々な管理業務が、システムの進化とともに自動化されていく安心感は、長期的な導入メリットの一つと言えるでしょう。
導入検討時に押さえるポイント
ICT導入を成功させるためには、事前の準備と計画的な進め方が重要です。以下の表に、特に注意すべきポイントをまとめました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 補助制度の活用 | 横浜市では「ICTを活用した見守り機器導入支援」で、1施設あたり最大16万円の補助があります(補助基準額は20万円)。 川崎市や相模原市でも類似の補助制度があるため、所在自治体の制度を必ず確認しましょう。 申請時期や条件を事前に把握し、計画的に活用することで導入コストを大幅に削減できます。 |
| 操作性への配慮 | PC操作が苦手な職員にもやさしいUI設計が重要です。Hoicは特に現場の声を反映した直感的な操作性が評価されています。 導入前に必ずデモ操作を行い、最もPCが苦手な職員でも使えるかどうかを確認することが成功の鍵です。研修体制やサポート体制の充実度も重要な判断材料となります。 |
| 業務棚卸・機能整理 | どの業務をICT化するか(連絡帳、登降園、勤怠、帳票作成など)を明確にし、複数製品を比較検討することが重要です。 CoDMONやNi+のように柔軟なカスタマイズ対応や自治体指定の提出帳票に対応できるツール選定がポイント。 現在の業務フローを整理し、最も効果が期待できる部分から段階的に導入することをお勧めします。 |
| 一度に全機能を導入するのではなく、段階的に職員の習熟を進めることが推奨されます。 まずは登降園管理から始めて、慣れてきたら連絡帳機能、その後に保育日誌機能といった具合に、無理のないペースで拡張していきましょう。 サポートセンターや定期研修を積極的に活用し、職員全員が安心して使えるまでフォローを受けることが成功の秘訣です。 |
ICT導入で変わる保育現場の未来
神奈川県内の多くの保育園でICT導入が進む中、その効果は数字以上に現場の「働きやすさ」や「保育の質」として現れています。手書きの連絡帳から解放された職員が「子どもたちの顔を見る時間が増えた」と語り、保護者からは「園での様子がよく分かるようになった」という声が聞こえてきます。
ICT導入は決してゴールではなく、より良い保育環境を作るためのツールです。システムを導入すること自体が目的ではなく、職員が本来の保育業務に集中でき、子どもたちにとってより充実した時間を提供できる環境を作ることが真の目的と言えるでしょう。補助制度を活用しながら、現場の声を大切にした段階的な導入を進めることで、きっと皆さんの園でも大きな変化を実感できるはずです。
「時間がない」を言い訳にしない。小さな積み重ねで変わる、保育の質と“学びの好循環”
質の高い保育をしている園は、日常の業務の中に「学び」を自然に溶け込ませています。時間や予算をかけなくてもできる、明日からの「職員研修」と「園内での学び合い」のヒントを紹介します。
職員室の空気が重い…チームの絆を深める「対話」のヒント
「なんとなく職員室の空気が重い」「情報の伝達ミスが続いている」「特定の職員同士がギクシャクしている…」 子どもたちの笑顔を守る保育の現場で働く「大人たち」の人間関係に悩まれる経営者や園長先生も多いよう…
先生たちの笑顔を守るために。園長・主任ができる心のケアとサポート
大切な仲間である保育士さんたちの「心の健康(メンタルヘルス)」を守るために、管理職に何ができるのか、今日から始められる具体的なアクションを一緒に考えていきましょう。


 ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。
ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。