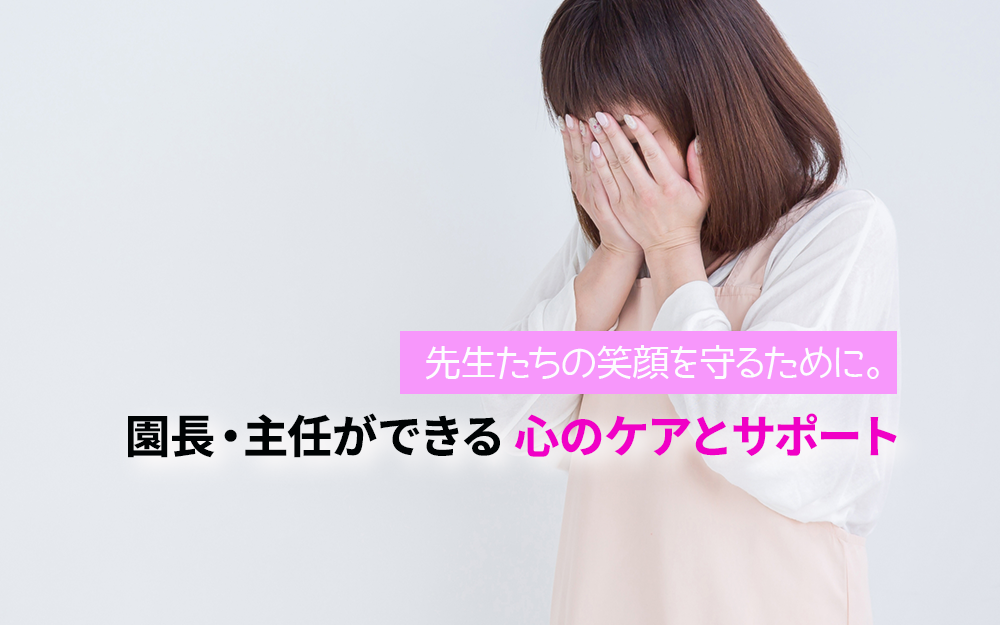保育園は、子どもたちの成長を支える大切な施設です。設計・建築には安全性や発達支援、地域との調和など、多岐にわたる専門知識と配慮が必要です。保育園を経営される方は、どのような設計事務所に依頼すべきか、どのように依頼すべきか悩んでしまうかもしれません。そこで本記事では、そのような経営者の皆さん向けに、保育園の設計・デザインにおける重要なポイントと、依頼するパートナー選びのポイントを事例を挙げながら解説します。
保育園の設計・デザインのポイントとは
保育園を設計・デザインするには、子どもたちの安全や成長、地域とのつながりを実現するために、他の施設とは異なる、独自の配慮が必要になります。
特に乳幼児期は心身の発達が著しく、環境からの影響を強く受ける時期。建築デザインが子どもの成長に与える影響はかなり大きいと思っていいでしょう。
安全性と衛生管理を徹底する
保育園の設計においては、安全性も重要です。保育園では転倒防止や衝突による怪我など日常茶飯事かもしれません。そういったリスクを防ぐため、施設内の隅やコーナーを丸めるデザインや、滑りにくい床材を採用することが必要になります。
発達段階にある子どもは、身体のバランス感覚が未熟で予期せぬ行動をとることも多くあるものです。細部にまで安全への配慮が求められるでしょう。
また感染症対策についても配慮が必要です。子どもの健康を守る上で最重要課題と言えるでしょう。
- 通路にゴムマットを使用し、角部にクッション性の高いパネルを設置することで、事故リスクを低減する
- 各所に手洗いや消毒設備を配置し、ウイルスや細菌感染対策を徹底する
空間設計で子どもの発達を促す
保育園ならではの重要な要素としては、子どもたちが自発的に遊び、学び、成長できる環境を作ることが挙げられます。ある程度の刺激を子どもたちに与える空間は、好奇心を刺激し、創造性や社会性を発達させる手助けになります。
子どもたちの活動内容は、年齢や発達によって大きく変わっていきますから、空間も柔軟に対応できるように設計しなければなりません。
- 広々としたリビングスペースと連動する移動式の仕切りを設置。遊び場と学習エリアを柔軟に変更でき、子どもの創造性を刺激
- 壁面にホワイトボードやカラフルなパネルを設置。子どもたちの感性に働きかける空間を実現
屋内外の環境を連携させる
建物の室内だけでなく、「外の空間」との連携を測ることも、保育園設計の大切なポイントです。
屋外活動は、運動能力を向上させたり、社会性を発達させるためには重要です。自然と触れ合うことは子どもの感性を育み、季節の変化を体感することにつながり、さまざまな学びを与える機会になるでしょう。
- 屋内から大きなガラス窓を通じて四季折々の自然を感じられるようにする
- 雨天時にも利用可能な半屋外スペースを設け、年間を通じた屋外活動や環境教育の機会を確保する
地域性と文化をデザインに反映させる
保育園は、その地域に根ざしている施設とも言えるでしょう。そのため、地域の文化や風土を反映したデザインを考慮するといいでしょう。子どもたちが、自分たちの住む地域を身近に感じられるようにすることで、地域への愛着が育まれ、地域コミュニティの一員として意識も醸成されます。
保育園を地域の人々との交流を促進することを意識して設計することで、子どもたちの社会性が育まれていくのです。
- 地域の伝統行事や郷土芸能をテーマにした内装を採用。壁面に地域の風景や昔話のイラストを配置するなど、地域のルーツに親しむ仕掛けを施す
参考サイト ユニップデザイン株式会社
SDGsにも配慮する
近年では、環境負荷を低減することが、保育園の設計においても重要なテーマになっています。これから子どもたちが生きていく地球環境を守るという観点を大人が率先して意識し、環境に配慮した設計を行うべきです。
もちろん、省エネルギー設計は運営コストを削減することにもつながる有意義な要素です。
- 太陽光発電システムの導入や高断熱性能の窓・外壁材の採用、自然換気を促進。エネルギー消費量を大幅に削減し、長期的な運用コストの低減と環境保護を両立する
保育園建設を依頼すべき建築会社・設計事務所の選び方
保育園の建設には、さまざまな要素が密接に絡みます。
建築においては、子どもの安全を最優先し、さらに運営が効率化させることや、将来的に発展させていくことも考慮すべきでしょう。メーカー・設計事務所を選ぶ際には、次のような強味をもつパートナーにプロジェクトを任せるのがおすすめです。
豊富な実績と専門知識を有している
これまでに多数の保育園、幼稚園、認定こども園の設計・建設を手がけ、蓄積されたノウハウで安全性、耐震性、バリアフリー対応、衛生管理などを確実に実現できる会社を選びましょう。多くの施工経験から得られた知見は、予期せぬ問題への対応力も豊かで、新たな課題解決のアイデアも多く蓄積していると考えられます。
保育園建設実績をもつメーカーなら、法令遵守はもちろん、現場でのフィードバックを反映して改善策を講じ、実際の運用面での細かい要望にも柔軟に対応してくれるでしょう。
参考サイト
三陽建設株式会社(保育園・幼稚園の施工実績多数、デザイン性と機能性を兼ね備えた提案が可能)
株式会社タカハシ工務店(木のぬくもりを活かした園舎づくり」に定評がある)
先進技術と革新的な設計を提案できる
最新の建築技術や素材、設備を積極的に導入し、従来の枠にとらわれない革新的なデザイン提案を行ってくれる会社を選びましょう。
今は技術革新のスピードが加速しており、保育現場のニーズも日々変化しています。それらに柔軟に対応できる技術力と創造性をもつ会社がいいでしょう。
ある設計事務所では、太陽光発電パネルを活用した自家発電システムの導入を提案しました。ICTを活用したセキュリティ管理システムや、保育士がタブレット端末で室内環境をリアルタイムにモニタリングできる仕組みなども実現してくれました。
参考サイト
株式会社日比野設計「幼児の城」(デザイン性と最新技術を融合した独創的な園舎。海外実績も豊富)
久米設計(ICT・防災・環境設計を取り入れた教育施設の先進事例)
費用管理が透明で、コストパフォーマンスが高い
保育園に限らず、建設には大きな初期投資が必要です。運用期間中のコスト管理も重要です。大手メーカーでは、坪単価や工事費の内訳を明確に算出し、予算内で最適なプランを提示することで、コストパフォーマンスの高い建設プランを立案してくれるでしょう。
長期的な視点に立った投資対効果を示し、将来かかる維持管理費用も含めて、総合的な費用計画を提示してもらえます。
参考サイト 保育園の建設費の相場・内訳・建築事例
万全のサポート体制がありアフターケアも充実している
建物は、竣工した後も、経年変化や使用状況に応じて様々な対応を行わなければなりません。
施設が完成した後も、定期点検や改修工事など、長期にわたって運用を支援してもらえるのは、やはり大手メーカーの強みです。
子どもが日常的に使用する保育園という施設では、安全性の維持が最優先事項となります。迅速で確実なサポート体制をとってくれる会社をパートナーとして選びたいところです。
完成後1年間の無償メンテナンス期間を設け、万が一の不具合にも迅速な対応を実施。定期的な点検体制により、施設が常に最適な状態で運営されるようサポートしてくれるような会社を選びましょう。
参考サイト アフター対応が良い建築事務所の例
柔軟なコミュニケーション、現場対応力を有している
保育園の建設は、さまざまな関係者の意見を調整しながら進める必要があります。そのためには円滑なコミュニケーションが必要となるでしょう。
プロジェクト初期から完成後の運営まで、発注者や現場スタッフ、地域の皆さんとも密なコミュニケーションを重視し、要望の変更や急なトラブルにも迅速に対応できる体制が整っているパートナーが理想的と言えます。
定期的な意見交換会を開催し、経営者や保育士、地域住民の意見を反映した設計変更を実施。現場でのトラブルを最小限に抑えているような設計事務所なら安心できます。
参考サイト 保育園ならではの設計・建築の基準
地域性を活かした提案力がある
大手メーカーの強みは、全国的なネットワークを有していることです。地域によって異なる気候や生活習慣、さらには保育ニーズにも柔軟に対応し、その土地に最も適している保育施設を提案してくれるでしょう。
たとえば、その地域特有の寒暖差に対応するために断熱性能の高い建材を採用したり、地域のお祭りや伝統行事をテーマにした内装デザインを提案してくれたりして、地域住民との連携を強め、地域に根ざした施設を目指してくれます。
参考サイト 地域性を重視してこども園や保育園を設計している例
保育園は子育て支援の拠点、子どもたちの成長の場
保育園の施設は単なるハコモノとはまったく異なるものです。それは子どもたちの未来を見すえた投資と言えるでしょう。初期費用だけでなく、長期的な運営コストや将来的な改修なども考慮に入れて総合的に提案してくれるパートナーを選びましょう。
この記事を参考に、保育園を経営する皆さんが安心してパートナーを選び、子どもたちの安全で快適な環境づくりと、地域に根ざした施設運営を実現していくことを願います。
保育園は地域の子育て支援の拠点です。未来を担う子どもたちの成長の場となる保育園を設計・建設してもらうパートナー選びを慎重に行ってください。

先生たちの笑顔を守るために。園長・主任ができる心のケアとサポート
大切な仲間である保育士さんたちの「心の健康(メンタルヘルス)」を守るために、管理職に何ができるのか、今日から始められる具体的なアクションを一緒に考えていきましょう。
“うちの園の良さ”、ちゃんと伝わっていますか?〜地域に愛される園になるための情報発信アイデア帖〜
園が持つ素敵な「らしさ」を、一貫した言葉と想いで、地域の方々へ丁寧に届けましょう。「これなら明日からできそう!」と思える具体的なステップに分けて解説します。高額な広告費をかける必要はありません。
書類業務が多すぎる!業務効率を上げるICT導入のリアル
絡帳の手書き、登降園記録の転記、保育日誌の作成…ICT化の波が広がっています。神奈川県内の具体的な導入事例、導入のメリット・注意点を紹介します。